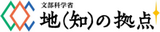2017.9.1
こんにちは!
MSFC『多文化共生チーム』です。
2017年8月10日に、第2回目の取材を行いました。
GES英会話で講師をされている、ペニー マタララバ先生です。
.................................................................................................................................................................................
|
名 前: ペニー マタララバ 出身国: フィジー 現在の勤務先: GES英会話 (http://www.ges-hiro.co.jp/index.html) Eメール: matararaba@gmail.com |
aaaaa |
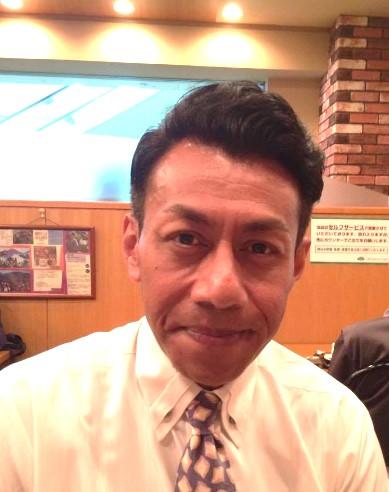 |
.................................................................................................................................................................................
インタビュー(2017年8月10日)
Q.フィジーという国はどんなところですか。
| A. | フィジーは、330くらいの島々から成り立っていて、面積は日本の四国と同じくらいです。 気候は、一年中夏ですが、日本より湿気は少ないと思います。 フィジーはもともとイギリスの植民地でした。 現在フィジーに住んでいるのは、主にフィジー人とインド人です。 その他、ヨーロッパ人やヨーロッパ人と他民族との混血、中国人、または近くの太平洋諸島の人々もたくさん住ん でいて、様々な人種の人々が住んでいます。 公用語は英語ですが、フィジー語やヒンディー語を話す人もたくさんいます。 また、観光地としても有名で、特にニュージーランド人やオーストラリア人がたくさん旅行に来ます。 |
Q.いつ日本に来ましたか。
| A. | 初めて日本に来たのは1987年で、当時18歳でした。 東京新宿にある、ホテルと観光の専門学校に通っていて、そこで2年半滞在しました。 日本に来る前から、フィジーの学校などで日本という国の話を聞いていて、ぜひ来たいと思っていました。 東京の専門学校を卒業した後は、フィジーに帰ってホテルマンとして働きましたが、5年ほど働いた後その仕事を 辞めてフィジーの大学に進学しました。 また、ラジオ局で働いたり、観光の専門学校で講師をしたりもしました。 そして2000年に再来日して、滋賀県彦根市の滋賀大学大学院に入学しました。 彦根では、近隣のコミュニティセンターやYMCA(Young Men's Christian Association; キリスト教青年会) でも講師をしながら、計7年間住んでいましたが、2007年から三重県松阪市のGES英会話で働き始めました。 |
Q.今の仕事について教えてください。
| A. | 火曜日から土曜日まで英語の授業を受け持っていて、いろんな年齢の生徒がいますが、大半が子供達です。 日曜日と月曜日は休みです。授業はほとんど松阪校で行なっていますが、木曜日だけは津校で教えています。 (訳者注:GESは松坂、津、伊勢で英会話教室を開いています。) 私は「技術・人文知識・国際業務ビザ(Engineer/Specialist in Humanities/International Services visa)」 という種類のビザで日本に滞在していますが、有効期間は一年ですので、毎年更新しています。 休みの日や平日の自由時間は、家でリラックスしたり、ジムに行って水泳をしたり、ボイストレーニングのレッスンを 受けたりしています。 職場では日本語を話す必要はあまりありません。 私は少し日本語を話せますが、講師は皆ネイティブの英語話者ですし、スタッフも全員英語が話せます。 私にとっては素晴らしい職場環境で、この仕事をとても気に入っています。 |
Q.日本での生活はどうですか。
| A. |
日本の生活はとても気に入っています。日本の文化、日本の人々、日本の食べ物など、すべてが大好きです。 |
Q.今三重大学にいる留学生にアドバイスはありますか。
| A. | 私からのアドバイスは、できる限り、日本の文化を学び、体験し、尊重し、これを受け入れることが大事だというこ とです。 そうすることで、日本での生活は居心地が良くなってくると思います。 言葉も理解できるようになれば尚暮らしやすくなります。 日本で仕事をしたいと思っている外国人の方にとっては、日本での労働に関する文化や環境について予備知識 を持っておくと、働きやすいと思います。 |